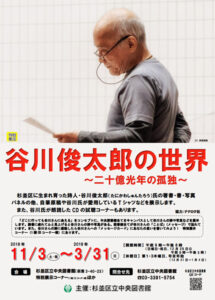想像してみよう。
「自分の住む町に大きな工場があり、もくもく煙を吐いている。ある日突然猫がよだれをたらし、激しく痙攣して海へ飛び込み、鳥が空から落ち、近所に住んでいる人たちが狂ったようになり奇声を発して次々に死にはじめる。両親も、子どもも狂死する。何とか生き残った住民たちはその侵害された身体を引きずりながらも、工場に排煙を止めるよう要求し国や県に訴える。工場は因果関係の証明がないとして訴えを拒否し、国も県も何の対策もとらない。むろん、住民たちの抗議の暴動が起こる。だが、警察は被害者を逮捕する。被害者は周辺の住民たちから徹底的に差別され続ける」ということを。
これが映画でも小説の世界ではなく、今から60年前に日本の水俣で起きた現実の出来事である。
水俣病とは何だったのか?
水俣病事件とはジェノサイド(大量殺害)だ。アウシュヴィッツが陸のジェノサイド、ヒロシマ・ナガサキが空のジェノサイドだったとすれば、ミナマタは海のジェノサイドである。ジェノサイドの本質とは、国家と産業の発展を優先させ、生命の尊重や人間の尊厳を二の次とする倒錯した政治にほかならない。
戦後日本の急速な高度成長は、チッソ(当時は新日本窒素肥料)の生産したアセドアルデヒドなしでは達成できず高度成長のためには、つまり「豊かさ」を追求するには、有機水銀を海にたれ流してもアセドアルデヒドの増産を中断することなく続ける必要があり、政府もそれを黙認した。それは一部の人間を犠牲にしてでも「豊か」になる社会システムだった。
「豊かさ」とは何なのか?
現代社会の支配的な価値観である効率主義や物質主義は、家族やコミュニティーをバラバラにひき離し、友情を忘れさせ、人びとが共有する未来について、あるいは自然とともに生きる人間の生き方について、考える時間を奪い去ってしまった。
もともと経済活動は、人間を飢えや病苦や長時間労働から解放するためのものであった。経済が発展すればするほど、ゆとりある福祉社会が実現されるはずであった。しかし、日本は金持ちになればなるほど逆である。人びとはさらに追い立てられ、自然はなおも破壊されていく。
効率を競う社会制度は、個人の行動と連鎖的に反応しあっているから、やがて生活も教育も福祉も経済価値を求める効率社会の歯車に巻き込まれるようになる。競争は人間を利己的にし、一方が利己的になれば、他の者も自分を守るため利己的にならざるを得ないから、人間は意地悪になったり欲張りになり、弱者をかばうこともなくなり、万人は万人の敵となり、自分を守る力はカネとモノだけになる。
自らの「問い」を生きていきたい。
「豊か」になる社会システムでは、政治家が寄生している企業があり、その企業は人権や自然を破壊してまで利益を追求する。企業には従業員がいて、消費者が存在する。自分自身やあなたがその従業員であり、消費者の一人なのである。水俣病事件は利己的な醜い自分自身を深々と映し出した。「豊かさ」の影で弱者が犠牲になるシステムに加担しないために、体現者たちの声を聞き、この時代に生まれた者として自らの「問い」を生きていきたい。
■緒方正人の「問い」
水俣病被害者で水俣病患者運動のリーダーだった緒方正人さんは「チッソは私であった」と語った。
「チッソとは何だったのかということは、現在でも私たちが考えなければならない大事なことですが、唐突ないい方のようですけども、私は、チッソというのは、もう一人の自分ではなかったかと思っています。私はこう思うんですね。私たちの生きている時代は、たとえばお金であったり、産業であったり便利なモノであったり、いわば「豊かさ」に駆り立てられた時代であるわけですけれども、私たち自分の日常的な生活が、すでにもう大きく複雑な仕組みの中にあって、そこから抜けようとしてもなかなか抜けられない。まさに水俣病を起こした時代の価値観に支配されているような気がするわけです。
この40年の暮らしの中で、私自身が車を買い求め、運転するようになり、家にはテレビがあり、冷蔵庫があり、そして仕事ではプラスティックの船に乗っているわけです。いわばチッソのような化学工場が作った材料で作られたモノが、家の中にたくさんあるわけです。水道のパイぷに使われている塩化ビニールの大半は、当時チッソが作っていました。最近では液晶にしてもそうですけど、私たちはまさに今、チッソ的な社会の中にいると思うんです。ですから、水俣病事件に限定すればチッソという会社に責任がありますけども、時代の中ではすでに私たちも「もう一人のチッソ」なのです。「近代化」とか「豊かさ」と求めたこの社会は、私たち自身ではなかったか。自らの呪縛を解き、そこからいかに脱していくのかというころが、大きな問いとしてあるように思います。」と自ら「問い」て、人として生きたい。一人の「個」に帰りたいという。
■原田正純の「問い」
水俣病に一生をかけて向き合った原田正純医師は、「水俣病の臨床的な研究をすることとなり、水俣を訪れたのが水俣病との出会いであったと。その最初の経験では、東京の豊かさと水俣の悲劇と貧しさの落差に愕然とした、治らない病気を前にして医者に何ができるか、何をすべきか」という患者からの深い問いかけに直面することとなった。医師と患者の関係は単に「治してあげる、治してくださいでしかないのか」と自らを「問い」た。無力である自分を突きつけられ、逃げず水俣病につきあうことを選択したという。そして「人類は、自然界には存在しない科学物質を開発し、気がついてみれば、私たちの周りには化学物質によって取り囲まれてしまっている。人間はどんでもない過ちを犯そうとしているのではないか。人類はもうこれ以上、何をどう便利に、豊かにしようというのだろうか。しかも、その恩恵に浴しているのは一部の人間だけである」と世界各地で公害病の調査研修をした、第一人者が強く批判している。
■山内豊德の「問い」
環境庁企画調整局長だった山内豊德さんは、水俣病認定訴訟において、国側の担当者となり、被害者側との和解を拒否し続ける立場にあったが、人間としての良心と、求められた官僚としての職責の間で悩み、1990年12月5日に自殺した。
山内豊德さんは、東京大学法学部を卒業して厚生省に入省した。中学生の時に骨髄炎にかかり身体はあまり丈夫でなかった。経済的には恵まれており、成績も抜群で、まさにエリート中のエリートではあった。しかし、生い立ちもふくめ、家庭的な愛情にはあまり恵まれて育たなかったため、社会的な弱者救済を設けられた厚生省を選んだという。
厚生省で福祉課長をしていた時代には、「人間はね、人を愛するという気持ちがなかったら人間じゃないよ・・・・。これは福祉に限ったことじゃない。行政に携わるすべての人間の基本は人を愛するという気持ちを持つことだよ」、「相手の心を汲み取って人に対処するようにしないといけない。自分の立場だけで判断していちゃ福祉の仕事は駄目だよ」と部下に語っていたという。
文学志向でもあったという山内豊德さんの15歳の時の詩がある。
【しかし】 山内豊德
しかし‥‥‥と
この言葉は
絶えず私の胸の中でつぶやかれて
今まで、私の心のたった一つの拠り所だった
私の生命は、情熱は
このことばがあったらこそ‥‥‥
私の自信はこのことばだった
けれども、
この頃この古葉が聞こえない
胸の中で大木が倒れたように
この言葉はいつの間にか消え去った
しかし‥‥‥と
もうこの言葉は聞こえない
しかし‥‥‥
しかし‥‥‥
何度もつぶやいてみるが
あのかがやかしい意欲、
あのはれやかな情熱は
もう消えてしまった
「しかし‥‥‥」と
人々にむかって
たゞ一人佇んでいながら
夕陽がまさに落ちようとしていても
力強く叫べたあの自信を
そうだ
私にもう一度返してくれ。
人は年齢を重ねていくにつれ、人は「しかし」という言葉を自分の中から失っていく。そして、その言葉を「だけど‥‥‥」という言い訳の言葉に変えながら生きていく。山内さんはそれが許せなかったのかも知れない。「しかし」と言えなくなった53歳の自分を、15歳の自分によって裁いてしまったのでないか。“もう一度返してくれ”という山内の叫びは、自分に向けてのものだったのか。「だけど」という時代へ向けてのものだったのか。
山内豊德さんは、加害者なのか被害者なのか。
福祉にとっての理想主義が経済優先の現実主義に圧倒されていく、その下降線の時代を山内さんは必死で生きようとしたのだと思う。高級官僚としてその下降に立ち会ったと責任においては彼はやはり加害者側の人間だったと言わざるを得ないし、又同時に時代の被害者だったとも言えるような気がする。彼はそのふたつのベクトルに引き裂かれながらアイデンティティの「二重性」を生きたのだろうと思う。少なくとも彼は自らの加害者性というものを痛みとともに鋭く認識していたはずである。それは彼が出した結論からも推測できる。しかし、これは彼に限ったことではなく、今という時代にこの日本という国で生きていくということは否応なくこの「二重性」を背負わざるを得ないということを意味している。ただ多くの人はこの内なる加害者性と向き合うことが辛くて、眼をそらしているに過ぎない。
この「二重性」を生きているという自覚こそが、そして開き直るのではなく、そこから出発する覚悟が私たちに求められている。そして、その辛い自己認識から眼をそらすことなく、私たちはその「二重性」と向き合う態度を身につけ、覚悟を持って生きなければならない。
被害者は苦しみながらも日本の未来に向かって自らを「問い」た。そして、多くの人間たちが水俣病から逃げずに寄り添い続けた。
しかし、加害者側の人間たちは自らの「問い」を生きていたのだろうか。チッソや行政の多くの人間たちは、有機水銀を海にたれ流していたことは知っていたはずだ。ジェノサイドとはナチスのアウシュヴィッツがそうだったように、決して悪魔のような人間が行うのではなく、普通の人間が自己保身のために行うものだ。アンブロース・ピアスの『悪魔の辞典』によれば、「会社」とは「個人が利益を得ながらも、個人的にいかなる責任も負わないで済むための巧妙な仕組み」というが、チッソや行政の人間が一人でも見てみぬフリをせずに早い段階で反対の声を発していたなら、ここまで被害が拡大することはなかっただろう。
水俣病は終わっていない
企業の責任は法的には明らかにされたが、企業の裏にある国や行政の責任が今なお明確にされていない。今までに一度も不知火海一帯の人たちへの健康調査すら実施しておらず、健康破壊の実態はわからないままだ。いじめが怖くて隠している人、チッソに気をつかってきた人、病気を我慢している人など、さまざま理由で取り残され苦しんでいる人たちがたくさんいいて、被害者救済は決してうまくいっていないのが現状だ。そうしたなかで、すでに多くの人が亡くなってしまった。
国や行政の責任が明確になり、すべての被害者が救済され、人間が差別されず自然と共生する地域社会を創造するまで、水俣病事件は終わることはない。
日本人は歴史に学ばない、歴史の教訓を生かさない。振り返らない。検証しない。後悔しない。反省しない。悩まない。やっぱり3.11の福島原発事故でも同じ過ちをくりかえした。不誠実な情報提供、責任の不追求、なし崩しの政策回帰、すべての生き物と自然の破壊。そして東電の経営者は現状の体制を維持すると決め、株主もたま原発の維持を承認した。これらすべてはこの国が水俣病事件から本質的に何も学んでいないという事実を突きつけている。歴史は繰り返す、という言葉をこれほどに再現した例は稀有だろう。
何よりも深刻なのは、子どもたちの健康被害だ。水俣病事件では、チッソが有機水銀をたれ流していた当時の子どもたちが今苦しんでいる。子どもたちの人権が守られなかったのが水俣病事件であり、国の論理では個人は守られないと証明されたのが水俣病事件である。
どうして、この国は「人を人と思わなくなってしまった」のだろう。子どもたちを守れないこの国に未来はない。そして、壊した自然は二度と元には戻ることはない。この国が辿り着く先には「豊かさ」という言葉だけが虚しく響くだけだろう。
決して忘れてはいけない言葉がある。
原田正純医師の「公害が起こって差別が生まれるのではなく、差別のあるところに公害が起きる」という言葉である。そして、「差別は必ず強い者から弱い者へと向けられていく」ということも。
水俣病は1956年4月、総合病院に狂躁状態を呈した5歳の少女、田中静子さんがかつぎこまれたことが始まりだ。そして、8日後には3歳下の妹、実子さんも同じ症状で入院した。
この姉妹の姉の下田綾子さんの手記によると「私の家は、チッソの排水口に近い水俣湾の坪谷にあって、すぐ下が海になっているんです。潮が満ちてきたら家から魚が釣れるぐらいです。上の妹の静子は当時5歳で、下の実子は3歳でした。静子はうちの中でも一番明るい子でした。近所の人が通れば、お茶も沸いていないのに「おじさん、お茶が沸いとるから飲んで行かんな」なんていうて人を寄らせていたんです。実子はいっつも「静子ねえちゃん、静子ねえちゃん」ちいって静子のあとをついてまわっていました。2人には海岸が遊び場、運動場だったんですよ。貝とかビナ(巻き貝)を採るのが好きで、船をつなぐ波止場に小さなカキがいっぱいつくんですけど、潮が引くと、すぐ二人で弁当箱とカキ打ちを持って行くんです。静子は上手だったから、2人分ぐらいはすぐ採って、実子にも食べさせていました。カキとかカラス貝なんかも毎日、味噌汁にして食べてました。いま考えれば、毒が入ったのを「美味しい、美味しい」ちいうて食べていたんですね。静子も実子もやっぱり魚は一番好きでしたから、たくさん食べていたんです。
(途中略)
熊大の病院に3年間入院してたんですが、脊髄から水を採ったときの怖さが頭にこびりついとったんでしょうか、ずっと目も見えないままで、ものもいえないし、手も足も曲がってしまって、身体もエビが曲がったようにしとったんです。そして昼も夜もずっと泣いて、泣きつづけて亡くなったんです。話せば淡々としてしまうんですけど、静子は本当に苦しんで死んだんです。口ではいえないくらしです。今日、熊本大学に保存してあった静子の脳の標本を初めて見ましてね、ひどく小さくなっていましたから無理もなかったんだなと思って、残念でたまりません」と無念さを語った。
静子さんは、病院にかつぎこまれてから3年後の1959年1月2日に亡くなった。実子さんは24時間、ヘルパーの介助を受けながら、水俣病の症状のある姉の綾子さん夫婦と一緒に暮らしている。
想像してみよう。
大人たちが有機水銀をたれ流した海で、何もしらない3歳と5歳の幼い姉妹が貝を採ってる姿を・・・。
参考文献
『証言水俣病』栗原彬 岩波新書
『水俣病は終わっていない』原田正純 岩波新書
『チッソは私であった』緒方正人 葦書房
『雲は答えなかった』是枝裕和 PHP研究所
(2018年11月24日)