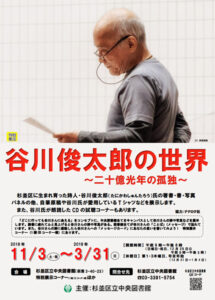段ボールに詰め込んであった詩集を整理してたら何冊かの『VOU』と『O』が出てきた。
いつ購入したのかも覚えていないこの詩誌のページをめくると「棚夏針手(たなかはりて)」の記述があった。
―― あまり知られていない詩人であるが、といって、それはむしろ当たりまえのことで、大正末期から昭和初期にかけての数年間、同人誌に発表したまま不明になった詩人である。それを鶴岡善久氏が周年に燃えて8年間をかけてまとめたのが『棚夏針手』である。鶴岡氏によれば、「サンボリックなものが形を解体しながらにシュルレアリスティックなイメージに変形していくところに棚夏針手のオリジナルな先駆者的な価値づけが生じてくる」といい、サンボリックからシュルレアリスムへ至るきわめて独自的な秘教的餐宴、といっている。わが国における直輸入的シュルレアリスム機関誌の発刊の前に、すでに彼のシュル開眼の活動は終りかけていた。つまり輸入以前に独自的に切り開かれていた。として高く評価し、またその発展的必然性をいちはやく実証していたということになるらしい。しかしわたしのみるところでは、ボードレール、ランボー、マラメル等の象徴主義がかなり強烈に働きかけ、そこへ日本的な美意識が、ひと癖ありげにまた生真面目に加えられて、あなたの皿に盛られた。そんな果物のようにみえる。それはシュルレアリスムがサンボリスムから必然的に発展する過程の詩の実証(近藤東言)であるよりは、やはり和風サンボリスムという感じが強いのである。日本のシュルレアリスムが衣裳として心を軽くしたとみるならば、棚夏針手の和風サンボリスムは、それ以前の、心の重みにあでやかな衣裳を着せかけているようにみえる。軽快な竹馬と靴のような関係である。ともあれ、現代詩への重要な足がかりをもつものとして意義深い。
「黒支那麦の婦人帽の内部」
黒い夕焼は
黒支那麦の婦人帽の内部。
黄金の渡守と語る白い巡礼が
初めて罌粟畑に下りた象牙の保護鳥のやうに
午終一面に張りつめた蜃気楼の帆陰で
見知らぬ昼の都会に狂ふ牛の胸の
燕脂色の第一闘牛賞のメダルを見る
それは月だ。
お前が私に贈ると云つて桃色の半巾(ハンケチ)に包んで置いた
基督磔刑像の痛々しい御胸だ。
密培の赤い象牙の保護鳥が啄むので
双手を伸べて抱擁の美眉術をつくさうとする夢が
石垣の氈襖(かもぶすま)の上を匂のやうに歩いて来る
月の常春(きずた)が軽く
背後の花壇は行手の泉にうつる。
それは薔薇の花。
お前の置いて行つた一本の金髪のからんで居る
基督磔刑像の蒼白めた御足だ。
不日(いつか)
久しく帰つて来ないお前が帰つて来て
私の「陶然」の客間(サロン)で
その黒い夕焼の婦人帽を脱ぐ時があらうも知れぬ。
私は 其時
畳まれた水色の粉油が
お前の耳かくしの束髪に雪のやうに積るのを
さうして白藻はお前に
快く眠られるだけの冬を招くのを
尚、魂が蝸牛(かたつむり)のやうな瑣瑙の手燭に
麹色の果汁氷果(アイスクリーム)を盛つて推(すす)めることを知つて居る。
けれど
黒い夕焼の婦人帽の内部の月と薔薇の都会の紫の蓋をした巨大な蒼白い密瓶の側面では
白い巡礼と黄金(きん)の渡守とが乳房をあはせ
その影の弁髪の密航者は
象牙の保護鳥を捕へんものと
黄金の泊木を空に灯してゐる
おお それは
黒い夕焼の月の常春藤(きずた)に懸(かか)つて
透蚕(きさご)のやうに皮膚を匿さんとなしつつ
悶えてゐるお前ではないのか。
「薔薇の幽霊の詞」
これは花粉色の絶筆の集である。
「今」の二月廿九日である。そして又、
「明日」の二月廿九日である。
私であるお前達の薔薇の幽霊であるモノタイプなのだ。
私は懇願した招待は嫌いだ。
これは私自身のための招待だ。
私はこの招待を衷心から寿つて呉れる数人に限つて、
嬉んでここにある幾個かの快い椅子を使用して欲しいと依頼したい。
私の範囲にゐる数人は嬰児の背後から偶然の催芽が神の平均を失はせる「真」を、
私は怕らくは知つて居やうから。
私はこの優れ行く盛花を禁断したくはないのだ。
私は恒に背後にゐる女(ひと)の像に乱祝であることを悲しむ。
けれど、
私は彼女のために斯うして何時ともなく創くられた
「巨大なるソロモンの櫃」の五穀の一握を、
一指づつ掌に啓いて行くことをゆえなく怕れる。
私は誰呼する。
私はこの手に
「明日」の二月廿九日の君臨を知つて居る神々の、
私であるお前達の、
EX.VOTEを支へ終はせたい、
私はアルチュール・ランボーの径に死んだ若い商人であるが。
これが私である薔薇の幽霊だ。
読者よ、私は直截に申します。
都(すべて)、常識を以て認識して欲しいと。
棚夏針手とはペンネームで、彼は本名を田中真寿という。
また彼には田中真珠というペンネームも用いた(これは堀口大学からの言葉もあって本名の真寿に戻る意味もあったらしい。昭和二年十二月の「近代風家」第二巻第十二号に発した「寝明り」、「星」などの作品にはこの田中新珠が使用されている)。棚夏針手は、そのほか「明星」、「詩と音楽」、「白孔雀」、「君と僕」、「指紋」、「青騎士」などの諸雑誌に作品を発表した。近藤東、竹内隆二、添田英二、大河内信敬などわずかに詩的交渉があった。活動期は大正十年代で彼の十九歳から二十代前期にかけてであったと思われる。とくに当時注目されたようでもなく、わずかに北原白秋、堀口大学などの詩人が雑誌の選者あるいは編集者として注目した程度であったらしい。棚夏針手のビオグラフィについては、まったくつまびらかではないが、わずかに竹内隆二の「作家・山本周五郎の生いたち」という文章のなかに、「桜橋の『高治』という親質屋には棚夏針手というのが居て、これの詩が当時シュルレアリスムの先駆となりました。」、「そのうち、添田英二と棚夏針手が与謝野晶子の「明星」に推薦され、北原白秋の「詩と音楽」に私と添田、棚夏が推薦となりました。」という記述がみいだせる程度である。残した作品はおそらく三十篇前後ほどで、当時彼は「薔薇の幽霊」という詩集を、二十一篇ほどの詩を集めて出版する計画であったらしい。が、これはついに実現しなかった。棚夏針手は二十代後半からおそらく詩からさっぱり離れたらしく戦後いささか左傾して青年文化運動にたずさわったりして、常磐線の牛久あたりにいるのではないかという推察も存在するが実際には彼の失われた足跡はまったくたどれない。(『棚夏針手詩集』蜘蛛社)
彷徨の青春時代はあきれるほどカラッポで、奴隷船のような部屋で小さな窓から波間の太陽を見上げるように、ダダやシュルレアリズムや幻想文学を読んでいた。妄想するとこによって現実から逃避するためである。奴隷船から海に飛び込んで何処かにたどりつくために必死で泳ぎ続けている。少しは泳ぎは上手にはなっているが・・・。
(2019年6月7日)