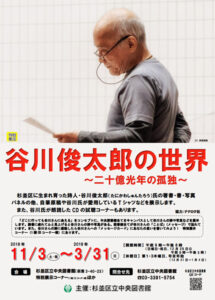「沖縄の辞書」 落合恵子
あなたよ
世界中でもっとも愛(いと)おしいひとを考えよう
それはわが子? いつの間にか老いた親? つれあい?
半年前からあなたの心に住みついたあのひと?
わたしよ
心の奥に降り積もった 憤り 屈辱 慟哭(どうこく)
過ぎた日々に受けた差別の記憶を掻かき集めよ
それらすべてが 沖縄のひとりびとりに
いまもなお 存在するのだ
彼女はあなたかもしれない 彼はわたしかもしれない
沖縄の辞書を開こう
2015年4月5日 ようやくやってきたひとが
何度も使った「粛々と」
沖縄の辞書に倣って 広辞苑も国語辞典も
その意味を書きかえなければならない
「民意を踏みにじって」、「痛みへの想像力を欠如させたまま」、「上から目線で」と
はじめて沖縄を訪れたのは ヒカンザクラが咲く季節
土産代わりに持ち帰ったのは
市場のおばあが教えてくれた あのことば
「なんくるないさー」
なんとかなるさーという意味だ と とびきりの笑顔
そのあと ぽつりとつぶやいた
そうとでも思わないと生きてこれなかった
何度目かの沖縄 きれいな貝がらと共に贈られたことば「ぬちどぅ たから」
官邸近くの抗議行動
名護から駆けつけた女たちは
福島への連帯を同じことばで表した
「ぬちどぅ たから、いのちこそ宝!」
「想像してごらん、ですよ」
まつげの長い 島の高校生は
レノンの歌のように静かに言った
「国土面積の0・6%しかない沖縄県に
在日米軍専用施設の74%があるんですよ
わが家が勝手に占領され 自分たちは使えないなんて
選挙の結果を踏みにじるのが 民主主義ですか?
本土にとって沖縄とは?
本土にとって わたしたちって何なんですか?」
真っ直すぐな瞳に 突然盛り上がった涙
息苦しくなって わたしは海に目を逃がす
しかし 心は逃げられない
2015年4月5日 知事は言った
「沖縄県が自ら基地を提供したことはない」
そこで 「どくん!」と本土のわたしがうめく
ひとつ屋根の下で暮らす家族のひとりに隠れて
他の家族みんなで うまいもんを食らう
その卑しさが その醜悪さが わたしをうちのめす
沖縄の辞書にはあって
本土の辞書には載っていないことばが 他にはないか?
だからわたしは 自分と約束する
あの島の子どもたちに
若者にも おばあにもおじいにも
共に歩かせてください 祈りと抵抗の時を
平和にかかわるひとつひとつが
「粛々と」切り崩されていく現在(いま)
立ちはだかるのだ わたしよ
まっとうに抗(あらが)うことに ためらいはいらない
沖縄と親交のある落合恵子さんは沖縄の基地問題にも関心があり「新基地はいらない」と沖縄が声を大にして訴えている。「本土との溝を共感で乗り越えたい」という思いから「沖縄の辞書」を発表したという。落合さんは、詩について「平和な日本を守るための自分との約束」と語り「共に歩かせてください」と述べている。「ただ、出会っても自分には帰れる場所が東京にあり、沖縄の人はそのまま暮らす。そこに自責の念がある。沖縄を忘れてはならないと自分に確認し、約束するしかない」と言い「傷め続けられてKちあ沖縄を防波堤にして、日本の安全や安定があるというのに」とも落合さんは話している。「沖縄の辞書」は2015年4月10日付の毎日新聞の夕刊に発表された。
落合さんが「沖縄の辞書」を書いたきっかけは、2015年4月5日の故・翁長知事と菅官房長官に会談である。
この会談とは、米軍普天間基地の名護市辺野古への移設問題をめぐり意見交換をしたものであり、2014年12月に辺野古移設反対の翁長知事誕生以降、政府は話し合いを避け無視をしてきたがようやく実現した対談である。
それにしても菅官房長官が知事に語った言葉は軽すぎる。「先に移設ありき」であるし、本気で考え吟味しているとは思えない。「辺野古移設を断念することが普天間の固定化につながる」と述べ、移設作業を「粛々と進めている」と語った。辺野古移設を「唯一の解決策」と言い張ることは、県外に移設先を求めないという日本政府の怠慢でしかないことである。
2015年11月、政府は翁長雄志知事の埋め立て承認取り消し処分は違法だとして、処分撤回け向け代執行訴訟を起こした。それにしても、一体誰が誰を訴えるべきなのか。政府が知事を訴えるとは噴飯物だ。行政不服審査法を恣意的に解釈して法の原則に反し、沖縄の選挙結果を無視して民主制にも背いたのは誰か。指弾されるべきは政府の方である。法治国家であることを自ら否定するような政府の対応は、沖縄県民の民意を踏みにじるためなら手段を選ばない、米軍基地の負担は、沖縄県だけに押しつければよいという、安倍内閣の明確で意思の表れにほかならない。
翁長雄志知事は、県民とともに、国の横暴に真っ向から立ち向かった。沖縄の民意をまったく認めない安倍内閣は、憲法九十二条「地方自治の本旨」に違反している。国と地方自治体は対等なのだ。
2018年8月8日、残念ながら翁長知事は膵臓がんのため亡くなった。心から哀悼の意を捧げます。
なぜこの国では、沖縄米軍基地に対する反対の声や批判の声があろとも、民意は絶対に尊重されず政策は強行されるのか。
沖縄でどれほど基地反対の声が高まろうとも、政府の態度は変わることがない。沖縄に限らず横田空域をはじめとして、日本全土が米軍によって好きなように使うことができる空間として規定されているという事実は、本土の人間の日常生活では滅多に意識さてないからである。基地を止められない理由はアメリカの意思と、米国に自発的に隷従することによって国内での権力基盤を強化しつつ対米追従利権をむさぼる官僚・政治家が日本の中枢部を牛耳っているという構造である。日本政府と米国の傀儡は法的に根拠づけられている。
基地は日米安保条約と地位協定が日本の国内法の上位に位置し、この優位性は法的に確立されている。戦後憲法には、民主主義の原則や基本的人権の尊重やらが立派に書き込まれている。しかしそれらは決定的な局面では必ず空文化される。なぜなら権力の奥の院——その中心に日米合同委員会が位置する——における無数の密約によって、常にすでに骨抜きにされているからである。つまり、この国には、表向きの憲法を頂点とする法体系と、国民の目から隔離された米日密約による裏の決まりごとの体系という二重体系が存在し、真の法体系は当然後者である。言い換えれば、憲法を頂点とする日本の法体系などに、大した意味はないのである。官僚・裁判官・御用学者の仕事とは、この二重体系の存在を否認することであり、それで辻褄が合わなくなれば二重の体系があたかも矛盾しないかのように取り繕うことである。この芸当に忠実かつ巧妙に従事できる者には、汚辱に満ちた栄達の道が待っているからである。
副島隆彦氏の『〔新版〕属国二本論を超えて』によると、日本政府は米国に対し「思いやり予算」として年間6500億円支払っているという。これ以外に国民の目の見えないところで、この10倍の7兆5000億円のお金が、いろいろな形で毎年米国に支払われているという。これらのお金はすべて日本人の税金である以上、基地問題は沖縄だけの問題ではなく日本全体の問題でもある。
日本は、米軍によって守られている、だから発展して平和だと思っているが、実際には日本を攻撃する国などはなく、抑止力のための軍事強化は世界中に戦争の危機感を高めるだけだ。ウィキリークスの暴露にした秘密公電によると、沖縄には海兵隊が1万3000人しかいないそうだ。もはや必要もない沖縄米軍基地のために莫大なお金を使うのはやめるべきだ。
日米開戦70年を総括するならば、戦勝国・敗戦国という米日の「主従関係」から日本がいかに抜けだし、国民の意味を基に国家政策を決定できる真の主権国家、独立国家、民主主義国家としての「日本」をどう構築するかが最大の課題といえるだろう。
(2018年12月17日)